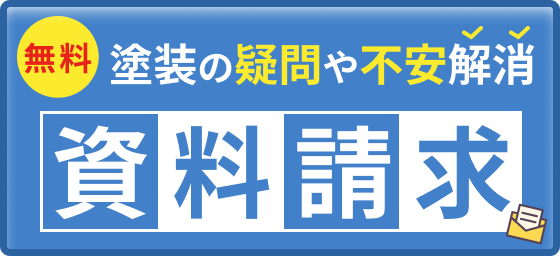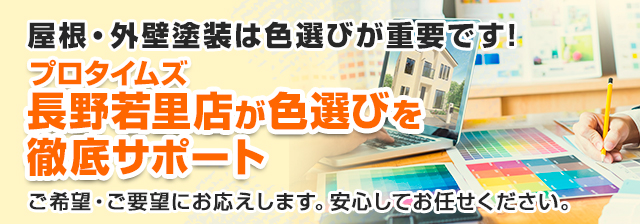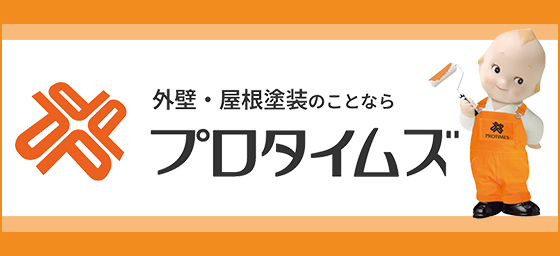スタッフブログ
防水工事の耐用年数とは?建物を守るために押さえておきたい基礎知識と対策
2025.07.21
防水工事
スタッフブログ

「屋上の防水って、前に工事してから何年経つんだろう…まぁまだ大丈夫かな?」なんて、つい後回しにしてしまうこと、ありませんか?
防水工事のことは普段意識しにくいので「きっとまだ平気だろう」と思いがち。
これ、防水工事でよくあることです。
しかし、防水層の寿命を過ぎて放置していると、ある日突然雨漏りが発生して「もっと早く手を打っておけばよかった…」と後悔する羽目にもなりかねません。
実は防水工事には耐用年数(=寿命)の目安があり、それを知って計画的にメンテナンスすることが建物を長持ちさせる秘訣です。
本記事では、不動産オーナーや施設管理者などプロ寄りの皆さんに向けて、防水工事の耐用年数に関する基礎知識と対策をわかりやすく解説します。
防水工事の種類ごとの寿命や特長、寿命を縮める環境要因、寿命超過によるリスク、そして費用感や税務上のポイント、メンテナンス方法まで網羅しています。
建物を雨漏りから守り、資産価値を維持するために、ぜひ最後までお読みください。
☑ 防水工事の耐用年数は種類や工法によって大きく異なる
☑ 防水工事の種類と特徴 シート防水、アスファルト防水、ウレタン防水
☑ 防水工事の耐用年数に影響を与える環境要因
☑ 防水工事にかかる費用の目安とコスト感
☑ 防水工事の耐用年数を意識して賢く建物を守ろう
防水工事の耐用年数はどのくらい?基礎知識を押さえよう

まず、「防水工事の耐用年数」とは何か、基本から押さえましょう。
耐用年数とは防水層(防水工事の効果)が持続する期間の目安を指し、平たく言えば「防水の寿命」のことです。
新品の防水層でも永遠に効果が続くわけではなく、経年劣化していずれ防水性能が低下します。
そのため定期的な再工事(や補修)が必要になりますが、そのおおよその周期を示すのが耐用年数です。
では耐用年数は何年くらいなのでしょうか?これが一概に「○年」と言えないのが難しいところ。
防水工事の種類や工法によって寿命は大きく異なり、一般に短いもので約10年、長いものでは20年程度が目安になります。
たとえば後述しますが、ウレタン塗膜防水(液体を塗るタイプ)は約10年前後、シート防水(シートを貼るタイプ)は10~15年程度(素材によっては最大20年)、アスファルト防水(複数層を重ねるタイプ)は15年前後~20年近く持つケースもあります。
もちろん実際の寿命は施工品質や環境条件によって前後します。あくまで「これくらい経ったら劣化が進むので注意しましょう」という目安と考えてください。
耐用年数を把握しておくことは、建物の維持管理にとって非常に重要です。
なぜなら、寿命を過ぎても防水層を放置すると雨漏りなど重大なトラブルを招きかねませんし、逆に寿命前に適切なメンテナンスや再施工を計画すれば雨漏り被害を未然に防ぎ、建物の寿命そのものを延ばすことができるからです。
「まだ大丈夫」と油断して耐用年数を超過させると手痛いしっぺ返しを食らうこともあります。
そうならないために、次章から防水工事の種類ごとの耐用年数と特徴を詳しく見ていきましょう。
防水工事の種類ごとの耐用年数と特徴(シート防水、アスファルト防水、ウレタン防水)
防水工事には大きく分けて「シート防水」「アスファルト防水」「ウレタン防水」の3種類があります。
それぞれ工法が異なり、長所や短所、そして耐用年数にも違いがあります。
まずは主要な防水工法ごとの一般的な耐用年数と主な特徴を一覧表で整理してみましょう。
| 防水工法 | 一般的な耐用年数(寿命目安) | 主な特徴・ポイント |
|---|---|---|
| シート防水(塩ビシート/ゴムシート) | 約10~15年程度(塩ビシートは最大20年程度) | 防水シートを下地に貼り付けて防水層を形成。工期が短く比較的軽量。紫外線に強い塩ビシートが主流。ゴムシートは伸縮性に優れるがやや耐久性劣る。 |
| アスファルト防水 | 約15年前後(工法により13~20年程度) | アスファルト(瀝青)を用いてルーフィングシートを複数層積層する昔ながらの工法。耐久性が高く寿命が長いが、施工に手間と時間がかかり重量も増す。 |
| ウレタン防水(塗膜防水) | 約10年前後(厚み・仕様により最大14~15年程度) | ウレタン樹脂の液体を塗って膜を作る工法。継ぎ目のない一体成形で複雑な形状の屋上にも施工しやすい。軽量で比較的安価だが、定期的なトップコート塗り替えが必要。 |
※上記はあくまで目安です。実際の耐用年数は施工素材の品質や立地環境、メンテナンス状況によって変動します。
では、それぞれの工法についてもう少し具体的に解説します。
シート防水の耐用年数と特徴

シート防水はその名の通り防水性のあるシートを屋上に敷き詰めて貼り付ける工法です。シートの素材には主に塩化ビニール樹脂(塩ビシート)と合成ゴム(ゴムシート)があります。
近年は耐候性(天候への強さ)の高い塩ビシート防水が主流で、ゴムシート防水は一昔前より減っています。塩ビシートは1.5~2.5mm程度の厚みでカラーバリエーションも豊富、一方ゴムシートは1.2~2.0mm程度で伸縮性に優れるものの鳥害や衝撃で破れやすい難点がありました。
シート防水の一般的な耐用年数は10~15年程度とされています(素材によって差があり、塩ビシートなら10~20年、ゴムシートで10~15年程度が目安。
紫外線や熱に比較的強い塩ビシートは寿命が長めですが、いずれにせよ10年を超えたあたりから継ぎ目のシール劣化やシートの浮き・剥がれなどの症状が出始めます。
メリットとしては工期が短く費用も抑えめであること、材料が軽量なので建物への負担が少ないことが挙げられます。
逆にデメリットはシートの継ぎ目部分からの漏水リスクや、下地の形状によってはシートが密着しづらい箇所ができることです。
ただし機械的固定工法(ビス留め)など施工方法を工夫すれば、下地との密着不良を防ぎ風でめくれないようにすることも可能です。
アスファルト防水の耐用年数と特徴

アスファルト防水は、ルーフィングシートと熱融解させたアスファルト(防水用瀝青)を交互に重ね、何層にも積み重ねて厚い防水層を作る工法です。
一般的に最も歴史が長く信頼性の高い防水方法とされ、多くのビルやマンションの屋上防水に採用されてきました。
複数層で構成されるため防水性能は極めて高く、破損しても下の層がカバーするなど耐久性・信頼性はピカイチです。
その分、材料と手間がかかり工期が長くコストも高め、加えて溶解アスファルトを扱うため作業環境(臭気や火気)の問題や仕上がりの重量増などのデメリットもあります。
アスファルト防水の耐用年数は15年前後がひとつの目安です。
実際には工法や仕上げによって寿命に差があり、例えば保護コンクリートで押さえた仕上げでは約17年、露出で砂を撒いた仕上げ(保護層なし)では約13年というデータがあります。
押さえコンクリートありの方が紫外線や熱から防水層を守れるため長持ちするわけですね。総じて他の工法より寿命が長め(15年以上持つケースも)ですが、定期点検を怠れば想定より早く劣化する可能性もあります。
ウレタン防水の耐用年数と特徴

ウレタン防水は、防水効果のあるウレタン樹脂の液体を現場で塗って硬化させる「塗膜防水」の一種です。
液状材料をコテやローラーで塗り広げるため、複雑な形状の下地や配管・段差の多い屋上でも隅々までシームレス(継ぎ目なし)に防水層を形成できるのが大きなメリットです。
仕上がりはゴム状の弾性膜となり軽量で建物に負荷をかけません。
またシート防水のようなジョイントがないぶん漏水リスクを低減できます。
デメリットとしては、液体ゆえに硬化乾燥に時間がかかる(工期中天候に左右されやすい)、経年で防水膜が硬化してひび割れしやすい、溶剤臭がある、といった点が挙げられます。
ウレタン防水の耐用年数は一般に10年前後とされています。
他の工法と比べるとやや短めですが、これはウレタン防水の場合トップコート(表面保護塗料)の劣化が寿命を左右するためです。
標準では5年前後でトップコートが劣化するので塗り替えが推奨されており、適切にトップコートを更新していけば防水層自体は10年以上もたせることも可能です。
実際、厚みを十分に確保したり高品質な材料を使ったウレタン防水では12~15年程度機能する例もあります。
ただしノーメンテナンスだと紫外線で表面が劣化・剥離し、10年未満で防水性能が低下してしまう恐れがあるため注意が必要です。
防水工事の耐用年数に影響を与える環境要因とは?

同じ工法で施工した防水でも、置かれた環境によって寿命が延びたり縮んだりします。
ここでは防水工事の耐用年数に影響を与える主な環境要因を見てみましょう。
- 気象(雨風・雪など):屋上は常に雨や風、時には雪や雹(ひょう)の影響を受けます。
大量の降雨で排水が追いつかず水たまり(冠水)が生じると、防水層に大きな負荷がかかり劣化を早めます。
強風で飛来物が当たって防水層が傷つくこともあります。積雪地域では雪の重みや融け残りの水分が長時間防水層に作用し、劣化を進行させることがあります。 - 日射(紫外線・熱):太陽からの強い紫外線は防水材料を徐々に劣化させます。
特にウレタンやアスファルトなど有機材料は直射日光で硬化・脆化しやすく、防水性能の低下に直結します。
また夏季の高温や冬季の低温による温度変化(昼夜の寒暖差、季節の寒暖差)も、防水層の伸縮を繰り返させてひび割れ等の劣化を促進します。 - 荷重や衝撃(物理的ストレス):屋上を人が歩く機会が多かったり、設備機器の据え付け・移動がある場合、その荷重や振動・衝撃が防水層に負担をかけます。
例えば点検時の人の出入り(歩行)、工具の落下、ベランダでの物置設置なども少しずつ防水面を傷めます。
鳥の爪やクチバシによるシート破れ(鳥害)も報告されており、意外な物理的要因が寿命を縮めることもあります。 - 施工環境・下地の状態:施工時の環境も耐用年数に影響します。
下地コンクリートが湿っている状態で施工すると密着不良を起こしやすかったり、施工不良があると本来の寿命より早期に不具合が出ます。
また、新築時からの構造の動き(建物の微妙な沈下や揺れ)による下地亀裂が防水層に影響するケースもあります。 - メンテナンス状況:環境要因とは少し異なりますが、日ごろの手入れも寿命に大きく関わります。定期点検や清掃を行い、早めに補修していけば寿命いっぱいまで性能を維持できますが、メンテナンスを怠ると劣化の兆候を見逃し、防水層のダメージが深刻化して本来の耐用年数より短く寿命を迎えることになりかねません。
以上のように、気候条件や使用状況、メンテナンスの有無によって防水層の寿命は変動します。
同じ材料でも、厳しい環境下では早めにメンテをしないと耐用年数を全うできないことがあります。
逆に環境が良好でこまめな手入れをしていれば、耐用年数以上に長持ちさせることも不可能ではありません。
防水工事後も安心しきらず、こうした要因を念頭に置いて防水層をいたわることが大切です。
防水工事の耐用年数を過ぎると起こるリスク

耐用年数を過ぎた防水層をそのまま放置すると、建物に様々なリスクが生じます。
具体的にどんな問題が起こり得るのか、主なリスクを確認しておきましょう。
雨漏りの発生
最も直接的なリスクが雨漏りです。防水層が劣化して防水機能が低下すると、屋上やバルコニーから雨水が建物内部に侵入します。
天井や壁にシミができたり、ポタポタと水滴が落ちてくるような被害が発生します。
雨漏りにより内装や備品が濡れて損傷したり、カビが発生して衛生環境が悪化する恐れもあります。
建物構造へのダメージ
漏れ出した雨水がさらに進行すると、建物の構造体にまで到達します。
鉄筋コンクリート造の場合、雨水がコンクリート内部に染み込んで鉄筋を腐食させ、構造耐力の低下を招く深刻な事態になりかねません。
木造の場合も木材が腐ったりシロアリ被害を誘発する可能性があります。
耐震性の低下や建物寿命の短縮にも直結するため、雨漏りを放置することは非常に危険です。
資産価値や信頼の低下
雨漏りは居住者やテナントにも直接被害を及ぼします。
天井からの漏水で住民の家具が台無しになったり、ビル内テナントの営業に支障が出るケースもあります。
その結果、オーナーと入居者の信頼関係の悪化を招きかねません。
「この建物は管理が行き届いていない」と評価されてしまえば、空室増加や賃料低下にもつながり得ます。
また、構造劣化が進めば建物自体の資産価値が下がってしまうことも大きなリスクです。
修繕コストの増大
防水の寿命切れを放置したばかりに雨漏りが起き、被害が広がってから対処すると、結果的に修繕コストが高くついてしまいます。
例えば、早めに防水層の再施工をしていれば数百万円で済んだものが、雨漏り後に内装や構造補修まで含めると倍以上の費用になってしまう、といったケースもあります。
事前に手を打つか後手に回るかで経済的な損失も大きく変わります。
このように、防水工事の耐用年数を過ぎたままにすることは百害あって一利なしです。
建物を健全に保つためにも、「そろそろ寿命かな?」と思ったら放置せず専門業者に点検を依頼し、適切な修繕・改修を行うことが肝心です。
防水層の劣化サインを見逃さず早めに対処すれば、雨漏りによる建物内部への被害や弱体化といった重大リスクを防げます。
耐用年数と税務処理の関係(修繕費と資本的支出)

防水工事の計画を立てる際、意外と悩ましいのが費用の会計処理です。
特に法人や不動産オーナーの場合、工事費用を一度に経費計上できるか(修繕費)、それとも資産計上して減価償却するか(資本的支出)で、税金面で大きな差が出ます。
多くのオーナーさまはできれば修繕費として一度に経費処理したいと考えるものです。
結論から言えば、防水工事の費用はケースによって「修繕費」か「資本的支出」かに分類されます。
税務上の判断基準は国税庁の通達に細かく定めがありますが、要点をかみ砕くと以下のようになります。
修繕費(しゅうぜんひ)
建物を元の状態・性能に維持または原状回復するための工事費用。
その年の経費として全額損金計上できます。
防水工事で言えば、既存の防水機能を回復・維持する範囲内の改修が該当します。
例えば防水層の部分的な補修や、同程度の性能の防水材での塗り替え・やり直し工事は修繕費として認められやすいでしょう。
資本的支出(しほんてきししゅつ)
建物の価値や機能を向上させるための工事費用。
資産計上して耐用年数に渡って減価償却する必要があります。
一度には経費にできず、毎年少しずつ費用化します。
防水工事では、従来より優れた防水性能を持たせる工事や付加価値を高める工事が該当します。
例えば「ウレタン防水から耐久性の高いアスファルト防水に変更して寿命を延ばす」ケースや「防水工事のついでに断熱材を追加して屋上の性能をグレードアップした」場合などは資本的支出と判断される可能性が高いです。
上記の分類を表にまとめると次のようになります。
| 会計処理区分 | 特徴(処理方法) | 防水工事の具体例 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 建物の維持・原状回復のための支出。発生年度の経費として全額損金計上可能。 | ・既存防水層の補修工事・同程度の性能の防水材で再防水工事・劣化箇所の部分補修 等 |
| 資本的支出 | 建物の価値・機能を向上させる支出。資産計上し、耐用年数で減価償却。 | ・防水材のグレードアップ(例:ウレタン→アスファルト) ([屋上防水工事は修繕費と資本的支出はどっち?節税対策まで解説! |
防水工事の多くは実務上「修繕費」で計上できるケースが多いと言われています。
なぜなら、屋上防水の再施工は建物の維持管理の一環であり、原状回復目的とみなされやすいからです。
とはいえ、上記のように工法変更で耐久性を大幅に向上させたり、明らかに付加価値をつけるような場合は資本的支出と判断されることもあります。
判断に迷う場合は事前に税理士や会計士に相談し、修繕費として処理できる範囲で工事プランを検討するのも一つの戦略です。
ちなみに、防水工事を資本的支出(資産計上)とした場合、その工事の減価償却期間(耐用年数)はおおむね10~15年とされています。
建物本体の法定耐用年数(RC造47年など)より短いため、防水工事費用を資産計上しても比較的早いペースで償却はできます。
しかし一度に全額経費にできる修繕費に比べれば初年度の経費化インパクトは小さくなります。
節税対策の観点では、可能な限り修繕費として処理したいのが本音でしょう。
そのためにも「性能向上ではなく劣化箇所の復旧」がメインであることを明確にして工事計画を立てるのがおすすめです。
いずれにせよ、耐用年数=再施工の目安を意識しつつ、コストの経理処理まで見据えて計画することが賢い建物管理と言えます。
防水工事費用の目安とコスト感(表で整理)

実際に防水工事を行うとなった場合、費用(コスト)も気になるポイントでしょう。防水工事の費用は、工法の種類や下地の状況、施工面積などによって変動しますが、ここでは主な防水工法について1㎡あたり単価の目安を示します。
屋上防水工事全般の単価相場はだいたい4,000~15,000円/㎡とかなり幅がありますが、平均的には1㎡あたり7,500~9,000円程度に収まるケースが多いようです。工法別の代表的な単価目安は次の通りです。
| 防水工法 | 平米単価の目安(税抜) | 補足事項・特徴 |
|---|---|---|
| ウレタン防水 | 約5,000~8,500円/㎡程度 | (密着工法の場合)下地に直接ウレタン樹脂を塗布。施工箇所の形状に左右されず対応可。通気緩衝工法など仕様によって単価上昇。 |
| シート防水 | 約4,000~8,000円/㎡程度 | (塩ビシートの場合)接着または機械固定でシートを敷設。材料費は比較的安価だが、下地平滑化やシート継ぎ目処理の手間あり。 |
| アスファルト防水 | 約4,500~8,000円/㎡程度 | (トーチ工法の場合)アスファルトシートを重ね貼り。工期長めで職人手間が多く単価高傾向。熱工法・トーチ工法など施工法で若干コスト差あり。 |
| FRP防水 (参考) | 約6,000~15,000円/㎡程度 | ガラス繊維強化プラスチックによる防水。ベランダなど小規模部位向き。材料費高めだが耐久性は高い(寿命12~20年)。 |
※上記単価は防水面積が中程度(100㎡前後)の場合の目安です。
面積が大きくなるほど平米単価は割安になり、小規模だとかえって割高になる傾向があります。
また、既存防水層の撤去の有無や下地調整の手間、立ち上がり部分の有無、地域や建物高さ(足場費用)などによっても総費用は変動しますので、あくまで参考価格とお考えください。
一般に、ウレタン防水やシート防水は比較的安価で、アスファルト防水はやや高価といった傾向があります。
しかし初期費用だけで判断せず、耐用年数やメンテナンス費用も含めたトータルコストで検討することが大切です。
例えばウレタン防水は安価でも寿命が短めなので、長期で見れば再施工回数が増えコスト増となる可能性があります。
一方アスファルト防水は高価でも寿命が長く信頼性が高いため、長期的には安心料込みと考えることもできます。
建物の用途や予算、求める耐久年数に応じて最適な工法を選ぶようにしましょう。
メンテナンスの重要性と耐用年数を延ばすコツ(点検・補修・トップコート塗替え)

最後に、防水工事後のメンテナンスについて触れておきます。
防水層は施工して終わりではなく、その後の手入れ次第で寿命が大きく変わります。
耐用年数を少しでも延ばし、トラブルを防ぐためのポイントを押さえておきましょう。
定期点検と清掃を欠かさずに
防水層の状態を定期的にチェックすることが何より重要です。
一般的には年に1~2回程度、専門業者または自分で屋上を巡回し、シートの継ぎ目や塗膜のひび割れ、浮きや剥がれがないか確認します。
またドレン(排水口)に詰まりがあると雨水が排水できず劣化を早めるので、落ち葉やゴミの清掃も定期的に行いましょう。
小さな異常に早く気付ければ、後述の補修で大事に至る前に対処できます。
劣化箇所の早期補修
防水層に軽微な破れやひび割れを発見したら、早めに補修することが大切です。
シート防水であればシートの貼り替えやシール増し打ち、ウレタン防水であれば補修用ウレタン樹脂の塗り足しなど、部分的な補修工事を迅速に実施すれば、防水性能の低下を最小限に抑えられます。
「まだ小さい傷だから大丈夫」と放置すると、そこから雨水が侵入して下地を痛め、補修では追いつかない大きな雨漏りに発展することもあります。
異変を見つけたらすぐ専門業者に相談しましょう。
トップコートの定期塗り替え
ウレタン防水やFRP防水の場合、表面に紫外線や摩耗から防水層を守るトップコートが塗られています。
このトップコートは防水層本体より短寿命で、5年前後で劣化することが多いです。
したがって、防水層自体は問題なくとも5年毎を目安にトップコートを塗り替えることをおすすめします。
トップコートを適切に更新すれば、防水層本体へのダメージを減らし結果的に耐用年数を延ばすことができます。
逆にトップコートを放置すると防水層が直接劣化し寿命を縮めるので注意しましょう。
シート防水でも、必要に応じて表面に保護塗料を塗るケースがあります。
その他の工夫
必要に応じて部分張り替えや重ね塗りといったメンテナンスも有効です。
シート防水なら劣化の激しい部分だけシートを張り替えたり、ウレタン防水なら全体の再塗装(オーバーレイ)を行うことで、防水層全体を作り直すより安価に寿命延長が図れます。
ただし繰り返し部分補修をしても限界はあるので、耐用年数を大きく超えている場合は思い切って全面的な再防水工事を検討した方が安心です。
このように、防水工事後も「点検し補修を行い保護塗替え」のサイクルでこまめに手を入れることが、結果的にコストを抑え建物を長持ちさせるポイントになります。
早期に劣化兆候を発見して対処すれば大規模改修の費用も抑えられます。
ぜひ「防水層も生き物」と捉え、定期的なお世話を欠かさないようにしましょう。
防水工事の耐用年数を意識して賢く建物を守ろう

防水工事の耐用年数について、その基礎知識から対策まで幅広く解説しました。
最後に内容を簡単に振り返ります。
防水工事には寿命(耐用年数)の目安があり、工法によっておよそ10年~20年と差があります。シート防水・アスファルト防水・ウレタン防水それぞれの特徴と寿命を理解し、自分の建物の防水層が今どれくらい経年しているのか把握しておくことが大切です。
耐用年数に影響を与える環境要因(天候や使用状況)も踏まえ、「何年頃に再工事が必要か」計画的に見通しを立てましょう。
そして寿命が来る前に適切なメンテナンスや更新工事を行うことが肝心です。
防水層の劣化を放置すれば雨漏りを招き、建物そのものの寿命を縮めるリスクがあります。
定期点検や補修、トップコート塗替えなどのメンテナンスを通じて耐用年数いっぱいまで性能を維持し、さらに延命を図る努力も重要です。
初期施工コストだけでなく、メンテナンス費用や税務処理(修繕費・資本的支出の違い)まで含めてトータルに検討すれば、きっと最適なタイミングと方法が見えてくるでしょう。
大切な建物を長持ちさせるには、防水工事の耐用年数を意識した賢い維持管理が欠かせません。
専門知識を押さえつつも日頃からアンテナを張り、「おかしいな?」と思ったらすぐ対策する姿勢で、雨漏り知らずの健全な建物を守っていきましょう。
あなたの建物管理のご参考になれば幸いです。
◇外壁塗装の疑問や施工のこと、価格などお気軽にお問い合わせください◇

フリーダイヤル 0120-460-461
メールでのお問い合わせはこちら⇩から
・お問い合わせフォームに必要事項をご入力の上「送信する」ボタンをクリックしてください。
・メールアドレスは正しくご入力下さい(弊社より返信メールをお送りします。)
。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。
ブログをご覧いただき ありがとうございます。
長野市・須坂市の塗装会社
株式会社霜鳥(プロタイムズ 長野若里店)です。
長野市・須坂市・千曲市・中野市・小布施町の
屋根塗装・外壁塗装ならお任せください!
塗装以外の内装リフォーム・お家のお悩み事も、
株式会社霜鳥にお任せ下さい!
。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。