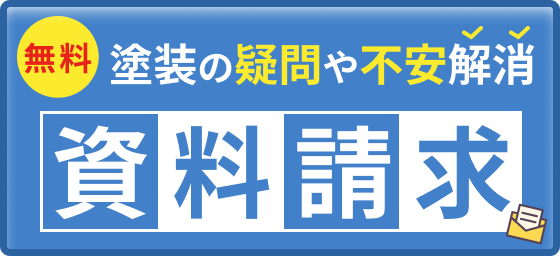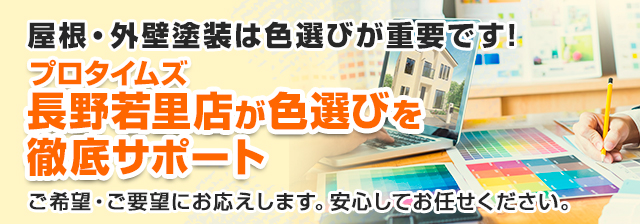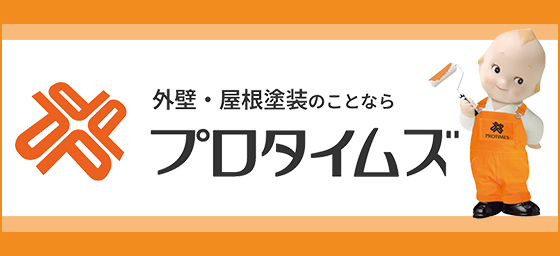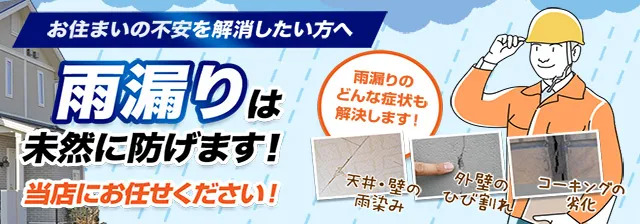スタッフブログ
【雨漏りの原因】雨樋のオーバーフローを防ぐ!原因と対策を詳しく解説
2025.07.03
雨漏り・雨漏する理由
スタッフブログ

「普段の雨なら問題ないのに、豪雨の時だけ雨樋からあふれてしまう」というご相談を受けました。
「このまま放置していると家に被害が出るのでは…」と心配になられたようです。
雨樋のオーバーフローは放置すると建物の劣化や雨漏りの原因となるため、早急な対策が必要です。
雨樋のオーバーフローは、適切な対策を知ることで、大切な住まいを雨水による被害から守ることができます。雨樋のトラブルを未然に防ぎ、安心して暮らせる環境を維持するために、この記事をぜひ参考にしてください。
☑ 雨樋のオーバーフローとは、雨水を排水できず、溢れ出てしまう現象
☑ 雨樋がオーバーフローする原因は、変形や破損、詰まり、容量不足、屋根のリフォームによる変化
☑ オーバーフローを防ぐには、定期的な清掃、必要に応じた修理や交換、適切な設計が必要
☑ オーバーフローが引き起こす、二次被害とは
雨樋がオーバーフローする主な原因
雨樋のオーバーフローとは、雨樋が本来の役割である雨水を排水できず、溢れ出てしまう現象のこと。雨樋がオーバーフローすると、住宅にとって深刻な問題を引き起こす可能性があります。
雨樋の変形や破損による影響

雨樋の変形や破損は、オーバーフローの主要な原因の一つです。
長年の使用により雨樋が歪んだり、台風や積雪の重みで破損したりすると、正常な排水機能が失われてしまいます。
変形した雨樋では水の流れが悪くなり、特定の箇所に水が溜まりやすくなります。
破損箇所からは水が漏れ出し、本来の排水経路を通らずに建物に被害を与える可能性があります。以下のような症状が見られる場合は要注意です。
● 雨樋の継ぎ目部分からの水漏れ
● 雨樋本体のひび割れや穴
● 支持金具の緩みや外れ
● 雨樋の傾斜不良による水の逆流
特に築10年以上の住宅では、経年劣化による変形が起こりやすくなります。
プラスチック製の雨樋は紫外線により脆くなり、金属製でも錆や腐食が進行するためです。
変形や破損を放置すると、オーバーフローによる二次被害が拡大するため注意が必要です。
落ち葉やゴミによる詰まり

雨樋のオーバーフローで最も多い原因は、落ち葉やゴミによる詰まりです。
特に秋の季節になると、大量の落ち葉が雨樋に蓄積され、水の流れを妨げてしまいます。
落ち葉以外にも、鳥の巣や砂、プラスチック片などの飛来物が、水の流れを阻害することがあります。
これらの詰まりが発生すると、雨水が正常に流れず、雨樋から溢れ出してしまうのです。
特に集水器や継手部分は詰まりやすく、少量のゴミでも水の流れが大幅に悪化します。
詰まりを放置すると、雨樋内の水位が上昇し、最終的にはオーバーフローが発生します。建物の外壁や基礎部分に水が流れ込むことで、深刻な被害を引き起こす可能性があります。
定期的な清掃により、このような詰まりは十分に防げるため、早めの対策が重要といえるでしょう。
雨樋の容量不足の問題

雨樋の容量不足は、建物の安全性を脅かす深刻な問題です。設計時に想定した雨量を超える豪雨が発生すると、雨樋の処理能力を上回る水量が流れ込みます。
ゲリラ豪雨など、近年の異常気象により、従来の設計基準では対応しきれない状況が増えています。
従来の基準では、1時間あたり100 mm程度の降雨強度(5〜6年に1度起きる豪雨)を想定する設計が一般的で、メーカー製雨樋のカタログにもその基準が記載されています。
しかし近年ではゲリラ豪雨の頻発に伴い、設計対象を150〜180 mm/h以上に引き上げるケースが増加しています。
築年数が古く、昔の基準で設計されている場合、ゲリラ豪雨ではオーバーフローによる雨漏りや軒天の損傷事故のリスクが高まります。
適切な容量の雨樋への交換や増設により、建物を水害から守ることができます。
屋根リフォームによる状況変化

屋根のリフォームを行った後に、雨樋のオーバーフローが発生するケースが増えています。
これは屋根の形状や材質の変更により、雨水の流れ方が変わることが主な原因です。屋根材を軽量なものに変更したり、勾配を調整したりすると、雨水の集まり方や流れる速度が変化します。
また屋根面積の拡張や増築により、雨樋に流れ込む雨水量が増加することも要因の一つです。
屋根リフォームの前に雨樋の容量を確認し、必要に応じて雨樋のサイズアップを検討すること。リフォーム後は屋根に合わせて雨樋の設置位置や勾配を再調整します。ほかにも専門業者による事前の流量計算を依頼するなどの対策を取りましょう。
屋根リフォーム時は雨樋への影響も含めて総合的に検討することが、オーバーフロー防止の鍵となります。
雨樋のオーバーフローを防ぐための対策

雨樋のオーバーフローを防ぐためには、適切な対策を継続的に実施することが重要です。
雨樋の機能を正常に保つことで、建物全体を水害から守り、長期的な住宅の価値を維持できるでしょう。
雨樋の定期的な清掃とメンテナンス

雨樋は、汚れが付着したり経年劣化したりするもの。そのため、定期的な清掃とメンテナンスが最も重要です。
面倒に感じるかもしれませんが、年に2回程度の清掃を行うだけで、深刻な水害を未然に防げます。降水量が増える梅雨の前や、落ち葉の季節の後に行うのがおすすめです。
● まず雨樋内の落ち葉やゴミを手作業で取り除きましょう。
● 次に、ホースで水を流して排水の流れを確認してください。
● 水の流れが悪い場合は、継手部分や集水器に詰まりがある可能性があります。
※高所作業が危険な場合は、無理をせず専門業者に依頼することをおすすめします。
● 毎年、清掃をするのも体力的に負担がかかりますので、専門業者に清掃を依頼した際に合わせて落ち 葉除けネットを設置するのも1つの対策につながります。ネットを設置する事で落ち葉の堆積を防ぐ効果に期待がもてます
メンテナンスでは以下の点をチェックします。
● 雨樋の傾斜が適切に保たれているか
● 継手部分にゆるみや破損がないか
● 支持金具がしっかりと固定されているか
● 雨樋本体にひび割れや変形がないか
特に台風シーズン前の点検は欠かせません。
小さな不具合でも放置すると、大雨時にオーバーフローの原因となってしまいます。
雨樋の修理や交換の必要性

雨樋は経年により劣化し、変形や破損の原因となります。これらの雨樋をそのまま放置すると、オーバーフローに留まらず、家そのものに甚大な被害をもたらすことになりかねません。
修理が必要な症状として、以下のようなケースが挙げられます。
● 雨樋に亀裂やひび割れが発生している
● 継手部分から水漏れが起きている
● 雨樋が変形して水の流れが悪くなっている
● 金具の腐食により雨樋が傾いている
雨どいの耐用年数は(素材によって異なりますが)20年程です。それを超えると経年劣化により破損、変形、破れ、金属の腐食などの不具合が発生しやすくなります。
一般に最も流通している塩化ビニール製の雨樋は紫外線に弱く、劣化が進むと破損することがあります。早期に対応すれば被害の拡大を防げるため、結果的にコストを抑えることができるでしょう。
雨樋の交換のタイミングの目安としては
● 雨樋の継ぎ目が取れている
● 雨水がうまく排水されない
● 設置から20年が経過している 場合は、雨樋の交換を検討します。
定期的な点検とともに、必要に応じて専門業者に相談することが重要です。適切な修理や交換により、雨樋本来の機能を回復させ、オーバーフローを根本的に解決できます。
適切な設計と設置で防ぐ

雨樋のオーバーフローを防ぐためには、最初の設計と設置が極めて重要です。
「うちの雨樋、雨が降るたびに溢れてしまう…」という悩みの多くは、実は設計段階での問題が原因。雨樋の設計には専門的な知識が必要です。
適切な雨樋設計では、屋根面積に対する雨水量を正確に計算し、必要な雨樋の断面積を決定します。
一般的な住宅では、屋根面積100平方メートルに対して直径125ミリメートル以上の雨樋が推奨されています。
また、雨樋がきちんと接続されていない、しっかり固定されていないなどの施工不良があった場合にもオーバーフローの原因になります。
地域の降水量データを参考に、集中豪雨にも対応できる余裕のある設計を心がけましょう。
雨樋のオーバーフローが引き起こす二次被害

雨樋のオーバーフローは、単なる水の溢れ出しで終わらず、住宅全体に深刻な被害をもたらす可能性があります。
適切な対策を講じなければ、建物の構造的な問題から健康被害まで、様々なトラブルが連鎖的に発生してしまうでしょう。
雨漏りのリスクとその影響

雨樋のオーバーフローが発生すると、最も深刻な問題として雨漏りのリスクが高まります。
「雨樋から水があふれているけど、まだ雨漏りしていないから大丈夫…」と考える方もいるかもしれません。しかし、雨漏りは目に見えない部分で進行していることが多く、発見が遅れがちです。
特に木造住宅では、継続的な水分により構造材の腐食が進み、建物の耐久性に重大な影響を与えます。
また、断熱材が濡れることで断熱性能が低下し、冷暖房効率の悪化にもつながります。
雨樋のオーバーフローを放置することは、単なる排水問題ではなく建物全体の安全性に関わる重要な課題といえます。
建物基礎の不安定化
雨樋のオーバーフローが続くと、建物の基礎に深刻な影響を与える可能性があります。
オーバーフローした雨水は建物の基礎周辺の土壌に浸透し、地盤を軟弱化させます。
特に粘土質の土壌では、水分を含むことで膨張と収縮を繰り返し、基礎に不均等な圧力をかけることに。
この現象が長期間続くと、基礎にひび割れが生じたり、建物全体が傾く原因となります。
基礎の修復は非常に高額な工事となるため、雨樋の適切な管理で予防することが重要です。
カビやコケの発生による健康被害

雨樋のオーバーフローが続くと、建物周辺の湿度が高くなり、カビやコケが発生しやすい環境を作り出してしまいます。特に日当たりの悪い北側や風通しの悪い場所では、カビやコケが繁殖しやすくなるのです。
カビが発生すると、健康被害のリスクが高まります。また、コケが外壁に付着すると建物の美観を損なうだけでなく、外壁材の劣化を早める原因にもなりかねません。
小さなお子様や高齢者がいる家庭では、特に注意が必要です。
ご近所トラブルの可能性
雨樋のオーバーフローは、単なる水の問題だけでは済まないことがあります。
特に隣接する住宅が近い場合、思わぬトラブルの原因となってしまうでしょう。
オーバーフローした水が隣家の敷地に流れ込むと、騒音問題や相手方の建物や庭に被害を与える可能性があります。
外壁の汚れや基礎部分への浸水、さらには隣家の植物を枯らしてしまうケースも珍しくありません。
特に集合住宅や住宅密集地では、階下や隣戸への影響が深刻化しやすくなります。
修繕費用の負担や法的責任を問われる場合もあるため、早期の点検と修理が重要でしょう。
まとめ:雨樋のオーバーフローは早期対策で被害を防げる

雨樋のオーバーフローは、単なる排水トラブルではなく、雨漏り・基礎劣化・健康被害・ご近所トラブルにまで発展する重大なリスクです。
原因は経年劣化や詰まり、設計不足など様々ですが、ゲリラ豪雨など局地的な災害が増えている今、その状況に合わせた家のメンテナンスをしっかりと行うことで、雨樋のオーバーフローを未然に防ぐことが可能です。
屋根のリフォーム、外壁塗装時、台風の後などは雨樋を見直す絶好のタイミング。まずは専門業者による点検や清掃から始めて、住まいの安心を手に入れましょう。
また、雨樋は自然災害によって破損するケースが非常に多い部材です。被害の原因が自然災害によるものの場合、プロタイムズ長野若里店では火災保険を使用した災害の修繕を行っています。
書類等の作成から工事までをワンストップで行っているので安心してご相談、ご依頼いただければと思います。
◇外壁塗装の疑問や施工のこと、価格などお気軽にお問い合わせください◇

フリーダイヤル 0120-460-461
メールでのお問い合わせはこちら⇩から
。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。
ブログをご覧いただき ありがとうございます。
長野市・須坂市の塗装会社
株式会社霜鳥(プロタイムズ 長野若里店)です。
長野市・須坂市・千曲市・中野市・小布施町の
屋根塗装・外壁塗装ならお任せください!
塗装以外の内装リフォーム・お家のお悩み事も、
株式会社霜鳥にお任せ下さい!
。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。